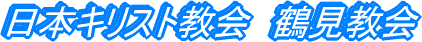今週の礼拝説教
2025年6月1日の説教
聖書:詩編110篇1-7節
使徒言行録1章9-11節
説教:「天に上げられた主イエス」 鶴見教会牧師 高松牧人
礼拝で使徒言行録を読み始めています。まだ慣れないこともあって、少しずつ読み進めています。使徒言行録はルカによる福音書の続きとして同じ著者が記した第二巻ですので、今日読んだ箇所も、ルカによる福音書の最後の部分と重なっているところです。
ルカによる福音書は、最後の24章の結びのところで、復活の主イエスが弟子たちに宣教を託され、聖霊を送ることを約束され、そして祝福の内に彼らを離れて天に上げられたことを記していました。使徒言行録の1章3~11節もそのことがもう一度語られています。そして、今日の9~11節は主イエスが天に上げられる場面です。ルカによる福音書の方にはこう書いてありました。「イエスは、そこから彼らをベタニアの辺りまで連れて行き、手を上げて祝福された。そして、祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神をほめたたえていた」(24章50~53節)。それがここで改めて、少し違う角度でほんの少し詳しく報告されています。
主イエスは天に上げられました。天に上るとか帰るとか召されるという言葉を、私たちは人が死んだときの婉曲表現として使うことがありますが、主イエスが天に上げられたというのはそれとは全く違うことです。主イエスは死んでしまわれたのではないからです。十字架に死んで復活された主イエスが、弟子たちに自らの生きていることを現わされた後に天に帰っていかれ、もう人間が地上で主イエスのお姿を見ることはできなくなったと言うことです。
ルカは先に福音書の方では、主イエスが復活後ただちに天に上げられたように書いていましたが、この使徒言行録の方では、復活された主イエスが折々に姿を現わされた期間が40日にわたっていたと書いています(1章3節)。その日数を明記しているのは、
使徒言行録だけです。主イエスが天に上げられたという出来事は、40日にわたる主イエスの特別な啓示期間の終了を意味いたします。主イエスはその後、いつの間にか、何となくどこかに消えて行かれたというのではなく、弟子たちの目の前で天に上げられて、もう決してその姿を誰も地上において見ることができなくなったと言うのです。
だから、主イエスの昇天という出来事は、主イエスが人としてこの世界にお生まれになったクリスマス、十字架で死なれた主イエスが復活されたイースターに続く、主イエスの私たちへの啓示の大いなる転換点なのです。そして、その10日後、復活の日から50日目のペンテコステに、主イエスが約束しておられた父からの贈り物、聖霊が弟子たちに下ることになるのです。
さて、使徒言行録の本文をたどっていきたいと思います。まず、9節には「こう話し終わると、イエスは彼らの見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった」とあります。最後の部分は直訳すると、「雲が彼を取り上げ、彼らの眼前から運び去った」と書いてあります。主イエスは雲に包まれるようにして、あるいは雲を乗り物にするかのようにして天に上げられたと言うのです。この光景を見る弟子たちの中の3人は、おそらく主イエスの生涯の不思議な一コマを思い起こしていたかもしれません。いわゆる山上の変貌の出来事です。弟子たちは、神の栄光に輝く主イエスと主と語りあうモーセとエリアの姿を一瞬垣間見たのでした。ペトロはこのすばらしい時がいつまでも続くことを願いましたが、それは許されず、すぐに雲があたりを覆い、栄光の主イエスのお姿は見えなくなってしまいました。雲は栄光の主イエスを包むものであり、同時に神の栄光の輝きを、罪深い人間の目から隠すものでした。
また、主イエスは弟子たちに、終りの日にご自身が再び来ることをお語りになりましたが、そこでこういう言い方をしておられます。「そのとき、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを、人々は見る」(ルカによる福音書21章27節)。このような雲は、その昔モーセが神からの言葉(十戒)をいただくために、シナイ山に登ったときに全山を覆いました。荒野を旅するイスラエルの幕屋の上にも留まって、主の栄光と臨在を示しました。さらに、ソロモンが神殿を完成させ、そこに主の契約の箱を安置したとき、雲が主の神殿に満ちたと聖書は書いています(列王記上8章10~11節)、
このような旧新約聖書の書き方から分かるように、昇天の主イエスを迎えて包み込んだ雲は、気象上の現象ではなく、人間の目には見ることのできない神の栄光を象徴していて、主イエスが雲によって弟子たちの眼前から運び去られたとは、主イエスが今や神と共にあり、神の栄光と力にあずかっておられることを示しています。
こういう写実的な描き方で主イエスの昇天を語るのはルカだけですが、パウロはこの
主イエスが天に上げられたという出来事を次のように歌いました。「だれがわたしたちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ、復活させられた方であるキリスト・イエスが、神の右に座っていて、わたしたちのために執り成してくださるのです」(ローマの信徒への手紙8章34節)。
この主イエスの昇天という出来事が、私たちの信仰の言い表しにおいても重要な意味をもつことは、私たちが礼拝の度に声を合わせて告白する使徒信条が、聖書のこうした言葉に導かれて、あのとても簡潔な表現の中で、主が「三日目に死者のうちから復活し、天に昇って、全能の父なる神の右に座しておられます」とはっきりと述べているところからも分かります。今日共に読まれた旧約聖書詩編110篇1節には、「わたしの右の座に就くがよい。わたしはあなたの敵をあなたの足台としよう」という主の言葉がありまいたが、神の右とは、主イエスが今や神と同じ権威と力をもって支配しておられることを現わす言い方です。天に上げられたとは、神の右の座に就かれたことであり、それは
神の御子イエス・キリストの勝利と凱旋を表しています。
ところで、使徒言行録は主イエスの昇天を記すにあたって、ここに天使と思しき白い服を着た二人の人を登場させ、神がその二人を通して弟子たちに語りかけられたことを記しています。人間の理解や説明を超える神の出来事が起こったとき、茫然と天を見上げて、そこに立ち尽くすほかない人々を支えるために、神は使者を遣わされます。彼らは弟子たちにこう告げるのです。「ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなたがたを離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる」(11節)。
これはルカが描くイースターの朝の出来事、あのお墓の前で、輝く衣を着た二人の人が現れて、婦人たちに語りかけた言葉を思い起こさせます。墓に駆け付けた女の人たちは、主イエスの遺体が見当たらないことに当惑していたのです。二人は言いました。「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたこと、お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず、罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている、と言われたではないか」(ルカによる福音書24章5~7節)。どうしてあなた方は、後ろを向いて、過去をなつかしむような行動をしているのか。二人の使者は、神の御業をまだ理解できず、途方に暮れている女の人たちの的はずれな思いと眼差しを正そうとしたのです。
たいへんよく似た言い回しが出て来るこの箇所でも、二人の使者は、弟子たちがこのことが理解できず、主イエスのお姿をもう見ることができなくなることで、何もしないでぼんやり天を見上げることにならないように、今こそ始めなければならない務めがあることに気づかせるためにこう語りかけたに違いありません。
すでに見たように、主イエスは天に帰っていかれるにあたって、後に残す弟子たちに
神が彼らを用いて進めようとしておられる御業を語っておられました。「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」(1章8節)。
弟子たちは、主イエスが語られたこれからの展望をしっかりと心に留め、父なる神が送ってくださる聖霊を待ち、聖霊の導きのもとに主イエスの御業を引き継いでいかなければなりません。
私たち信仰者は、神を天の父と呼び、主イエス・キリストが上げられた天を仰ぎ見て生きる者たちです、しかし、それは不安げに天を見上げることではなく、また地上の務めや戦いを忘れてぼんやりと天を見つめたり、あこがれたりすることではありません。
むしろ、地に足を踏まえ、冷静に地上の事柄に対処していくことが求められています。
なぜ、そうするのか、どうしてそうできるのか、それは私たちにとって天がもはや得体のしれないところでも、無気味なところでもなくなっているからです。天は、私たちを縛りつけたり、脅かしたりする冷たい運命の言い換えではありません。私たちにとっての天は、私たちのただ中に来られ、私たちのために十字架につき、私たちの罪を贖い、赦し、新しい命を授けてくださったお方が、働き、執り成していてくださるところです。
私たちはそのような天を知っているのです。主イエス・キリストの勝利と支配を知っているのです。先ほど、私たちはパウロが、復活された主イエスが、神の右の座っていて、わたしたちのために執り成してくださるという恵みを語るローマ書8章の言葉を思い起こしました。それに続けてパウロは、「だれが、キリストの愛からわたしたちを引き離すことができましょう。艱難か。苦しみか。迫害か。飢えか。裸か。危険か。剣か」と歌い、「しかし、これらすべてのことにおいて、わたしたちは、わたしたちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。わたしは確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高い所にいるものも、低い所にいるものも、他のどんな被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです」(8章35~39節)と歌い上げました。パウロは、主イエス・キリストがおられるまことの天を仰いでいました。愛する主を天にもっているということ、主が天におられることを知っているということは、何と心強く幸いなことでしょうか。
さらに、二人の証人たちは、天に上げられた主イエスが、「天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる」との約束も弟子たちに告げました。主イエスは離れたままでも行きっぱなしでもないのです。主は再び来られて、主イエスの復活と勝利の確かさを、私たちの救いと世界の完成によって現わしてくださるのです。私たちは、主イエスが最後を締めくくってくださるという希望と安心感をもって歩み始めることができるのです。
使徒言行録は、ルカによる福音書と重なっている部分をこれで終えて、これから主イエスの姿も見えず、声も聞くことのできない中で、使徒たちが新しい働きを始めていく様子を伝えてくれています。ペンテコステの聖霊降臨の出来事は2章に書かれていますが、1章後半には、彼らが主イエスの命令に従ってエルサレムを離れず、一緒に集まって祈りを合わせ、さらにユダが欠けてしまったために、十二使徒の補欠選挙をしたことが記されています。彼らは自分たちのなすべきことを考え、働き始めました。ですから、
主イエスが天に上げられたことは、寂しいことではなく、神の救いの御業の新しい時の始まりでした。主イエスの昇天によって、主イエスは特定の限られた場所だけにではなく、ご自身の霊を私たちに送ってくださることによって、世界中どこにでも臨み、働き、執り成してくださることになりました。世界中、すべての教会において、礼拝に主イエス・キリストが臨在くださるのです。私たちはいつどこにいても、復活された主イエスと共に歩むことができるようになったのです。主イエスの昇天から、聖霊が降って、教会が誕生し、教会の歴史が始まっていきます。主イエス・キリストの福音が人々の証しと奉仕によって全世界に広がっていくことになったのです。私たちも今、主イエスの昇天と再臨という時の間を、聖霊の導きによって福音の証し人として歩んでいるのです。