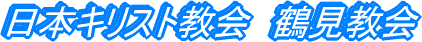今週の礼拝音声と礼拝順序
2025年10月19日の礼拝音声(当日礼拝後12時頃から)
2025年10月19日のYouTubeライブ配信(当日10時20分頃から、静止画のみ)
通信状況により音声が不安定となることがあります。
礼拝後に公開する 「礼拝音声」の方もご活用ください
※直近のものは、一番下にあります
●10月19日(日) 主 日 礼 拝
奏楽
招詞 (詩編96:1-3)
讃詠 546
信仰告白 (使徒信条)
讃美歌 9
聖書 レビ記19章11-18節 (旧約192頁)
マタイによる福音書19章13-30節 (新約37頁)
祈り
讃美歌 242
説教 「天の国に生きる」 牧師 高 松 牧 人
祈り
讃美歌 243
献金
主の祈
頌栄 541
祝祷
報告
☆今週の祈りの課題「家族全員礼拝のために」
2025年10月19日の説教
聖書:レビ記19章11-18節
マタイによる福音書19章13-30節
説教:「天の国に生きる」 鶴見教会牧師 高松牧人
第三主日にはマタイによる福音書を読んでいますが、今日は普段のテキストの区切り方に区切り方に比べると、ずいぶん長い箇所を一気に読んでいただきました。いつものやり方なら、13~15節、16~22節、23~30節と3回くらいに分けて説教するところかもしれません。それぞれの箇所に、有名なあるいは心にかかる主イエス・キリストの御言葉が書かれているのです。
けれども、今日これらを続けて読んだのは、一続きに読むことによってこれらに一貫した主題が貫かれていることを聴き取ることができればと考えたからです。個々の物語を読むだけでは、ひょっとすると聞き逃すかもしれない私たちに対する主イエスの御心を聞いてみたいと思ったからです。最初の段落は、主イエスが子どもたちを連れて集まってきた人々を叱るのですが、主イエスは子どもたちを来させなさいと言われ、祝福される話です。それに続くのが主イエスのところにやってきた「金持ちの青年」の話です。真面目に熱心に宗教的な問いを携えてやってきた若者が、主イエスの言葉を聞いて、悲しみながら立ち去っていくのです。その後、主イエスは弟子たちに、「金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい」と言われ、弟子たちは「それでは、だれが救われるのだろうか」と驚くのです。いずれも聖書を長く読んできた人たちにはよく知られている話だと言ってよいでしょう。これらの話はこの福音書だけでなく、マルコとルカの福音書にも出てきます。しかも、三つの福音書とも同じ順番で一つながりに記されています。ということは、これらの話は全然別の話のようですが、切り離して読むことのできないテーマがそこにあることに気づかざるを得ません。そのテーマは「天の国」(「天の国」というのは、「神の国」と同じ意味ですが)に生きるとはどういうことか、ということです。そして、それらはみな主イエスに従っていこうとしている弟子たち、ひいては私たちに向けて語られた教えであるということができるでしょう。これら一連の主イエスの言葉から、いったい天の国に生きるとは、信仰を持って生きるということはどういうことかを聴き取っていきたいと思います。
第一の話は、子どもたちを連れて主イエスのところにやってきた人々を、弟子たちが叱って追い払ったというところから始まっています。それは、子どもたちが弟子たちにまとわりついて、ただでさえ忙しい主イエスを煩わせてはいけないという配慮からであったかもしれません。しかし、その背後にはこんな子どもたちに主イエスの言葉や教えは分かるはずもない、主イエスが子どもたちに関わるのは時間の無駄だという考えがあったのでないかと思われます。当時の社会では、子どもの数は多かったのですが、そもそもその地位は低く、子どもたちの人権や意見が尊重されることはありませんでした。弟子たちも子どもたちはまだ神のことが分からない無価値な存在だと見なしていたのです。けれども、そのような通念を打ち破るようにして、主イエスは言われました。「子供たちを来させなさい。わたしのところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちの国である」(14節)。
子どもを祝福してくださる主イエスの話は、主イエスのご生涯の忘れられない一コマ
であり、私たちが好ましく、喜ばしく聴くことができるメッセージでしょう。しかし、
この御言葉が、子どもたちを払いのけようとした弟子たちに対して語られた言葉である
ことを思うとき、ここには私たちの考え方に対する根本的な問いが投げかけられていることに気づかざるをえません。シュラッターという新約学者は、この注解の中で「子どもたちがその弱さのゆえに神の国にふさわしくないのではなく、かえって弟子たちはその強さのゆえに神の国にふさわしくないのである」と書いています。私たちは、ここで改めて、天の国は自分が何がしかのものを持っていると思いあがっている者にではなく、何も持たず、それゆえに神のあわれみと恵みにひたすらより頼む者にこそふさわしいのだということを知らされます。
第二の話は「金持ちの青年」の話です。彼は、永遠の命、そしてそこにつながっていくことができる完全な生き方を熱心に求めていました。それで主イエスのもとにやって来て、尋ねたのです。「先生、永遠の命を得るには、どんな善いことをすればよいのでしょうか」(16節)。しかし、主イエスが「もし命を得たいのなら、掟を守りなさい」と言われ、その掟というのも彼が小さい時からよく知っており、守ってきていることばかりであったので、彼はがっかりして「そういうことはみな守ってきました。まだ何か欠けているのでしょうか」(20節)と問いました。それに対して、主イエスは「もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから、わたしに従いなさい」(21節)と言われました。すると、「青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである」(22節)とあります。
この若者は真面目で熱心な人でしたから、もし主イエスがたとえば、あなたの収入の10分の1をきっちり捧げなさい、あるいはお金持ちなのだから、半分を貧しい人に施しなさいとお命じになったとしたら、たぶん喜んでそうしたのではないでしょうか。彼は自分のために、自分の命を手に入れるためには、そうしたに違いないのです。しかし
主イエスは彼に施しという徳を積み重ねて来なさい、と言われたわけではありません。
主イエスは彼に、自分のもっているものに頼らず、ただ主なる神に信頼し、主イエスと共に歩むことを求められたのです。主イエスは、この若者が宗教的に熱心であるにも関わらず、神に向かって未だ本当に心を開いていない姿をご覧になり、それを妨げているのが彼の力と才能と恵まれた地位とその結晶とも言うべき財産であることを見抜かれて、「持ち物を売り払って」と命じられたのでした。彼は、主なる神さまの前に、自らの無力さと貧しさをこそ知る必要があったのです。
この青年のように、家柄、学歴、地位、熱心さにおいて秀でた人にパウロという人がいました。皆が羨むようなものをたくさんもっていました。しかし、パウロが復活の主に打ち倒され、その後、生まれ変わって新しい歩みを始めたときパウロは言いました。「わたしにとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失と見なすようになったのです。そればかりか、わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさに、今では他の一切を損失とみています。キリストのゆえに、わたしはすべてを失いましたが、それらを塵あくたと見なしています」(フィリピ3章7~8節)。金持ちの青年も、パウロも、そして私たちも、究極のところで人生のよりどころをどこに置くのかが問われているように思われます。
立ち去っていく金持ちの青年を見送りながら、主イエスが弟子たちに言われた言葉は有名です。「はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい」(23~24節)。
弟子たちはこれを聞いて非常に驚いて言います、「それでは、だれが救われるのだろうか」(25節)。主イエスがそこまで厳しいことを言われるのであれば、自分たちだって
立ち去るほかないではないか、と思うのです。だがそれに対して主イエスは言われます。
「それは人間にできることではないが、神は何でもできる」(26節)。主イエスが彼らを「見つめて」言われたということには、弟子たちに伝えようとしておられる熱い思いが込められています。「人間にできることではないが、神にはできる」。すなわち、救いとは、天の国に入るとは、自分の持っている知恵と力でそこに到達することではありません。自分の信仰の熱心さで勝ち取ることでもありません。主なる神さまは、どうしようもない私たちを、ご自身の真実と力によって捕らえ、圧倒し、ご自身のものとしてくださったのです。その神の驚くべき愛の御業の中で、私たちが何ごとかができたとか、できなかったということは意味を持ちません。私たちには不可能なのです。けれども、神は何でもできる、その約束にすがるほかないのです。
ところが、弟子たちは主イエスの言われることに恐れと不安を持ちながらも、自分たちはあの金持ちの青年とは違う、自分たちはもう主イエスの弟子にしていただいている
のだ、という優越感をもっていたようです。だから、ペトロはまた弟子たちを代表して言うのです、「このとおり、わたしたちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。では、わたしたちは何をいただけるのでしょうか」。自分たちは、実際に網を捨て、舟を捨て、それまでの生活や家庭を置いて、ひたすら主イエスに従ってきたではないか、と言うのです。よく言うなと思いますが、いかにもペトロらしい、向こう意気の強い、
あつかましい言い方です。けれども、ここで主イエスはペトロをお叱りにならず、弟子たちの思いや願いを否定してはおられません。それどころか、終りの日においては、彼らの思いにまさる約束が与えられることを告げておられます。「はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなたがたも、わたしに従って来たのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ」(28-29節)。
もちろん、彼らはまだ本当には何も捨てていないことに気づかねばなりません。その終りの日に至るまでに、彼らの功績も、誇りも、意気込みもすべて粉々に砕かれてしまわなければなりません。主イエスは、近い将来、弟子たちがご自身を裏切り、全く挫折して逃げ去ってしまうことも見越した上で、彼らが自分たちの可能性を一切なくしたところで、彼らがただ神の憐れみと赦しと御力によって立ち直り、終りの日を迎えることができるであろうと約束しておられるのです。
弟子たちの、主イエス・キリストへの服従も「人間にできることではないが、神は何でもできる」という約束のもとでのみ可能だということを忘れてはなりません。捨てることも、ついて行くことも、「神は何でもできる」と言われる方によって成し得ているのです。主のあわれみと恵みによってのみ、私たちは弟子として立ちうるのです。
「人間にできることではないが、神は何でもできる」。神の可能性は、人間の可能性を追求するところから来るのではなく、むしろ人間の可能性が閉ざされてしまうところから始まるのです。これは聖書全体を貫いている大きなメッセージです。アブラハムとサラ夫妻に男の子が与えられると約束されたとき、サラはひそかに笑いましたが、主はアブラハムに言われました、「主に不可能なことがあろうか」(創世記18章14節)。また、主イエスがこの世に来られるにあたって、受胎告知を受けたマリアは「どうしてそんなことがありえましょうか」と戸惑いましたが、天使ガブリエルは「神にできないことは何一つない」と告げ、マリアは「お言葉どおり、この身になりますように」と答えたのでした(ルカ1章37~38節)。この言葉は聖書全体にこだましています。
信仰に生きる、主の弟子として生きるとは、天の国に生きることです。そして、天の国に生きるとは、何も持たないものとして、ただ神のあわれみと恵みにより頼んで生きて行くことです。使徒パウロは言いました、「わたしを強めてくださる方のお陰で、わたしにはすべてが可能です」(フィリピ4章13節)。この神の可能性を信じて、私たちも歩んでまいりましょう。
新型コロナウィルスへの対応の一環として、やむを得ず礼拝に出席できない方のために
新たにYouTubeによる主日礼拝のオンライン配信と今週の礼拝音声の公開を開始しました。
また、毎週の礼拝終了直後(12:30ごろまでに)速やかに音声ファイルをアップロードする予定です。
※再生の途中で停止するなど、うまく再生できない場合には、音声ファイルをダウンロードしてから再生してください。
※音声ファイルの公開方法(参考情報)